
古都・京都の名スポットに光る、気鋭の美術館
「福田美術館」
京都・嵐山といえば、観光客に大人気の定番スポット。
渡月橋に竹林に人力車。京都らしさを味わえる場所として、いつ行っても賑わっていますよね。
そんな嵐山に、2019年にオープンした新しい美術館があるのをご存じでしょうか?
その名も 「福田美術館」。
……なんですが、ここ、ただの新設美術館じゃありません。
かなり“攻めてる”美術館なんです。
コンセプトは「100年続く美術館」。
時代を超えて愛される名作を収蔵しつつ、展示スタイルは柔軟。
日本画と西洋画を同じ空間に並べるなど、“常識にとらわれない”のがこの美術館の面白さです。

日本画なのに写真が撮影OK!
そして何より、注目したいのが 写真撮影OK(一部除く) なところ。撮った作品はSNSにアップロードすることも可能。
日本画って、基本はカメラNGのイメージありませんか?
ここではスマホで気になる作品をパシャっと撮ってOK。もちろんフラッシュはNGですが、気軽に思い出に残せるのは、今っぽくていい感じ。
日本美術を軸にしつつ、企画や見せ方は新しい。
そんな“伝統と革新のハイブリッド”を、自然豊かな嵐山で体験できるなんて贅沢ですよね。
観光のついでにふらっと寄るもよし。
アート目当てでガッツリ訪れるのもよし。
ちょっと感性に刺激を入れたいなってときに、かなりおススメの美術館です。

所蔵作品の見どころをちょっとご紹介
福田美術館の収蔵品は、日本画好きにはたまらないラインナップ。
伊藤若冲、与謝蕪村、竹内栖鳳、竹久夢二……名前を見るだけでワクワクしてきますよね。
ここからは、そんなコレクションの中でも注目の作品をいくつかピックアップしてご紹介します。
気になる作品があれば、ぜひ現地でじっくり鑑賞を!
紹介する作品は所蔵品のうちの極一部です。所蔵品は企画展ごとに入れ替えがありますので、美術館を訪れる際には美術館のHPを確認することをお勧めします。→福田美術館HP
伊藤 若冲(いとう じゃくちゅう)
《蕪に双鶏図》

作品解説(クリックまたはタッチ)

伊藤若冲は、江戸中期を代表する人気絵師のひとり。
動植物をモチーフにした作品が多く、なかでもその緻密さとユニークな構図は群を抜いています。
そして若冲といえば、やっぱり鶏(にわとり)。
彼の作品に何羽登場するんだというくらい、鶏モチーフはおなじみ。よほど好きだったんでしょうね。
この《蕪に双鶏図》にも、堂々と描かれた二羽の鶏が登場します。
とくに中央の鶏のポーズが印象的で、羽の流れ、脚の動き、表情の力強さまで、とにかくリアル。
カメラももない時代に、ここまで動物の特徴的なポージングが描けるって…観察力と描写力、どちらも尋常じゃありません。
背景に描かれた蕪の葉にも注目。
虫食いや変色といった細かな表現までしっかり描き込まれていて、リアルだけどどこか構図が装飾的。
この“写実と美意識のミックス”が、若冲らしいセンスです。
ちなみにこの作品、発見されたのはなんと2019年。
構図やタッチから、若冲が30代の頃に描いた初期作と考えられているそうです。
本格的に画業に専念するのは40代以降なので、それ以前の作品が見られるのはかなり貴重。若冲ファンならぜひチェックしておきたい一枚です。
動き、細部、色づかい——どこを取っても若冲の魅力が凝縮された一作です。
曾我 蕭白(そが しょうはく)
《雲龍図》(1771~1781年)

作品解説(クリックまたはタッチ)
曾我蕭白(そが・しょうはく、1730〜1781)は、江戸時代の中でもひときわ目立つ“クセ強め”な絵師。
特に水墨画の分野では、自由奔放でちょっと風変わりな作風で知られています。
この《雲龍図》も、そんな蕭白らしさがぎゅっと詰まった一作。
まず目を引くのが、大きな楕円を描くような構図。大胆すぎて一瞬戸惑うんですが、よく見るとこの曲線が画面全体に動きを出していて、視線が自然にぐるっと回るようにできているんです。
そして見逃せないのが、画面上部の龍の顔。
暗雲の中からひょっこり顔を出していて、なんとも言えない表情をしています。
ちょっとコミカルな感じもあって、「怖い」というよりは、妙に人間くさい。細部はしっかり描き込まれていて、ユーモアと緻密さのバランスが絶妙です。
一見すると勢いまかせに見えるかもしれませんが、構図の組み立て方や墨の使い分けにはしっかり計算があって、蕭白のセンスと技量の高さを感じます。
型破りだけど、ただ奇抜なだけじゃない。
曾我蕭白の“遊び心と本気”が詰まったこの一枚、現地でじっくり味わってみてください。
狩野 探幽(かのう たんゆう)
《雲龍図》(1666年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

狩野探幽は、江戸時代初期を代表する狩野派の絵師。
祖父の狩野永徳が豪壮華麗な画風で名を馳せたのに対して、探幽は一転、余白と静けさを大切にした、品のある画面構成で知られています。
この《雲龍図》は、そんな探幽が晩年に描いた作品。
一見すると“静”のイメージが強い探幽ですが、この龍はなかなかに迫力があります。
真正面をにらむようなその顔。輪郭線には墨の濃淡が巧みに使われていて、空間にふわっと浮かび上がるような立体感があります。
対して、雲の表現はとても繊細。
にじみやぼかしを駆使して、蒸気のような質感を生み出しており、荒々しい龍との対比で空気に緊張感が生まれています。
余白も探幽らしくたっぷりと。
描かれている部分と、描かれていない“空白”とのバランスが絶妙で、そこからじわじわと迫るような静かな迫力が伝わってきます。
静けさの中に潜む力強さ。
探幽の成熟した筆が生み出した、静寂と迫力が両立した龍図です。
与謝 蕪村(よさ ぶそん)
《猛虎飛瀑図》(1767年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

与謝蕪村は、俳人として有名ですが、実は画家としても一流。
独学で絵を学びながら、俳句の感性を絵の中にも取り入れていった、“詩と絵の二刀流”です。
そんな蕪村が描いたこの《猛虎飛瀑図》。
タイトルはなかなか勇ましいですが、出てくる虎は……ちょっと愛嬌のある姿。
実は当時の日本には本物の虎がいなかったため、蕪村たち画家は、輸入された虎の毛皮や敷物を参考に想像で描いていたんです。
その結果、背骨の位置や目の形など、どこか違和感のある部分もちらほら。
でも、それが逆にユニークな魅力になっているんですよね。
猫っぽいポーズや、ちょっととぼけた表情がなんとも可愛らしく、どこか漫画的な味わいもあります。
構図もおもしろくて、前景に竹を大胆に配置し、背景に滝を流すことで画面に奥行きを出しています。
細部よりも全体の雰囲気を大切にしているのが、蕪村らしいところ。
写実からはちょっと外れているけれど、そのぶん豊かな詩情があふれた一枚。
蕪村の“描く俳句”とも言えるような作品です。
竹内 栖鳳(たけうち せいほう)
《金獅子図》(1906年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

竹内栖鳳は、明治から昭和初期にかけて活躍した日本画家。
日本画の伝統を大切にしつつ、西洋画のリアリズムや技法も積極的に取り入れた、革新的な存在でした。
1900年、パリ万博の視察で渡欧した栖鳳は、現地の画家たちから大きな刺激を受けます。
特に衝撃を受けたのが、ジャン=レオン・ジェロームによるライオンのスケッチ。
その迫力に惹かれた栖鳳は、予定を延ばしてまで動物園に通い詰め、ライオンの徹底的な観察と写生を始めます。
帰国後、その成果を発揮するように、栖鳳はライオンをモチーフにした作品を次々と制作。
この《金獅子図》もその代表作のひとつです。
画面いっぱいに描かれた金色のライオンは、まさに“迫ってくる”ような構図。
鋭い牙や爪、たてがみの量感など、描き方は一見シンプルに見えて、実は写生に裏打ちされたリアルさが光ります。
奥行きのある構成と大胆なカットが相まって、画面全体から緊張感がにじみ出ています。
当時の日本では、ライオンといえば“唐獅子”のような想像上の存在が一般的。
そんな中で、リアルなライオンを真正面から描いたこの作品は、見る人に強いインパクトを与えました。
伝統的な日本画に、西洋の写実精神と現地での体験を融合させたこの一作。
竹内栖鳳のチャレンジ精神が詰まった名品です。
竹内 栖鳳
《猛虎》(1930年)

作品解説(クリックまたはタッチ)
竹内栖鳳といえば、写生重視のリアルな動物画で知られる画家ですが、
彼のもう一つの大きな特徴が「省筆(しょうひつ)」と呼ばれる表現スタイル。
余計な線は使わず、必要最低限の筆で本質だけをとらえる——そんな引き算の美学です。
この《猛虎》も、その省筆の技法がはっきりと現れた一作。
《金獅子図》と似た構図ながら、こちらはより線が簡潔で、色彩もすっきりとした印象。
特に虎の輪郭線はとてもシンプルで、それなのにちゃんと力強さも伝わってくる。
胸もとの毛並みの柔らかさも、最小限のタッチで見事に表現されています。
ただ、タイトルは「猛虎」と言いながら、この虎、実はあんまり“猛”じゃありません。
首をかしげて上を見上げるしぐさがなんとも愛らしくて、むしろちょっと人懐っこい雰囲気さえあります。
栖鳳は、単にリアルさを追求するのではなく、動物の仕草や瞬間の表情をどう見せるかを大事にした画家。
この作品からも、虎をじっくり観察し、どこに魅力があるかをしっかり見極めていたことが伝わってきます。
一筆一筆を絞り込んで、動物の“らしさ”だけを残す。
省略の中に宿る表現力が、栖鳳ならではの味です。
フランス近代絵画も、ちょっとだけ。
福田美術館といえば日本画のイメージが強いですが、実はこっそり(でもしっかり)フランス近代絵画も所蔵しています。
こういうところにも、“常識にとらわれない”というコンセプトを見出すことができますね。
紹介する作品は常設展示されているわけではありません。美術館を訪れる際にはHPをご確認ください。→福田美術館HP
クロード・モネ
《プールヴィルの崖、朝》(1897年)

作品解説(クリックまたはタッチ)
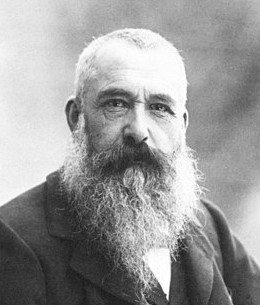
ノルマンディー地方の海岸線に立つ断崖と、光をたっぷり受けた海。
やわらかい朝の光に包まれたこの風景は、印象派の巨匠クロード・モネが繰り返し描いたお気に入りのモチーフのひとつです。
モネは、幼い頃をフランス北西部のル・アーヴルという港町で過ごしました。
そのため、ノルマンディーの海には特別な思い入れがあったようで、ディエップ近郊のプールヴィルも何度も訪れ、海と崖の風景を繰り返し描いています。
この作品もそのひとつで、朝のやわらかな陽光が崖に差し込み、海の色も淡く、やさしく揺らいでいます。
輪郭はあえてぼかされ、空気と光の移ろいを感じさせるような表現。
まさに“印象派”らしい、瞬間の空気をとらえた一枚です。
カミーユ・ピサロ
《エラニーの積み藁と農婦》(1885年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

福田美術館の西洋画コレクションには、印象派のもう一人の重要人物、カミーユ・ピサロの作品も含まれています。
ピサロは1884年、パリから北西にある小さな村・エラニーに移り住み、そのまま終生を過ごしました。
この作品は、そんな彼の“エラニー時代”の一枚。
農婦の働く姿と、高く積まれた「積み藁」。
印象派らしいやわらかい光が全体に広がっていて、素朴で静かな農村の日常が穏やかに描かれています。
明るく自然な色づかい、そして筆のタッチは細かく丁寧。ピサロの画風が、次第に精緻さを増していく過渡期であることがうかがえます。
このあと彼は、スーラらの影響で点描技法を取り入れる“新印象派”の時代へと進んでいきますが、
この作品にはその入口となるような繊細さと、自然への深いまなざしがすでに感じられます。
福田美術館の基本情報

所在地:京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町3−16


コメント