
ゴッホの作品の中でも、とくに人気のある一枚が《夜のカフェ・テラス》。
南フランス・アルルで描かれたこの絵は、日本でもCMやアニメの背景として使われることが多く、見たことがある!という方も多いのではないでしょうか。
この作品の一番の魅力は、なんといってもその色づかい。
テラスを照らす鮮やかな黄色と、深く澄んだ青い夜空。このコントラストが、アルルの夜を幻想的に演出しています。
でも実は、こんなにカラフルな画風になる前、ゴッホはまったく違う作風で絵を描いていました。たとえば、オランダ時代の代表作《ジャガイモを食べる人々》(1885年)を見てみると、その違いは一目瞭然です。
同じ“夜”を描いた絵なのに、こちらは暗くて重厚な雰囲気。色もくすんだ茶色や灰色が中心で、まるで別人が描いたかのようです。
いったい、ゴッホに何があったのでしょう?
どうして彼は、重苦しい色合いからあんなにも鮮やかな夜へとたどり着いたのか——。
この記事では、2つの「夜のカフェ」作品を中心に、ゴッホの画風の変化とその背景をわかりやすく紹介していきます。

《ジャガイモを食べる人々》(1885年)
アルル以前のゴッホはどんな絵を描いていた?
ゴッホといえば、ビビッドな黄色の《ひまわり》や幻想的な《夜のカフェ・テラス》を思い浮かべる方も多いですよね。でも、そんな鮮やかな色づかいを始めたのは、実は南フランス・アルルに移ってからのことなんです。
それ以前のゴッホは、どんな絵を描いていたのでしょうか? 時代をさかのぼって、彼の変化をたどってみましょう。
オランダ時代:暗く重い色にこめた想い

ゴッホが画家を志したのは、1880年、27歳のとき。
当時としてはちょっと遅めのスタートでしたが、そこから亡くなるまでの約10年間、彼は驚くほどの熱量で作品を生み出していきました。
画家としての初期、ゴッホが強く影響を受けたのは、農民の生活を描いたジャン=フランソワ・ミレーらバルビゾン派の画家たち。彼自身も、農民や炭鉱夫など、働く人々をテーマにした絵を多く描いています。
たとえば有名な《ジャガイモを食べる人々》は、まさにこの時期の代表作。
色合いは全体的に暗く、茶色やグレーが中心で、どこか物悲しさを感じさせます。それは、農民たちの過酷な生活をリアルに、誠実に描こうとしたゴッホのまなざしそのものだったのかもしれません。
けれど、絵は売れず、家族や周囲との関係もうまくいかず……。
1885年、ゴッホはさまざまな葛藤を抱えたまま、故郷オランダを離れる決断をします。
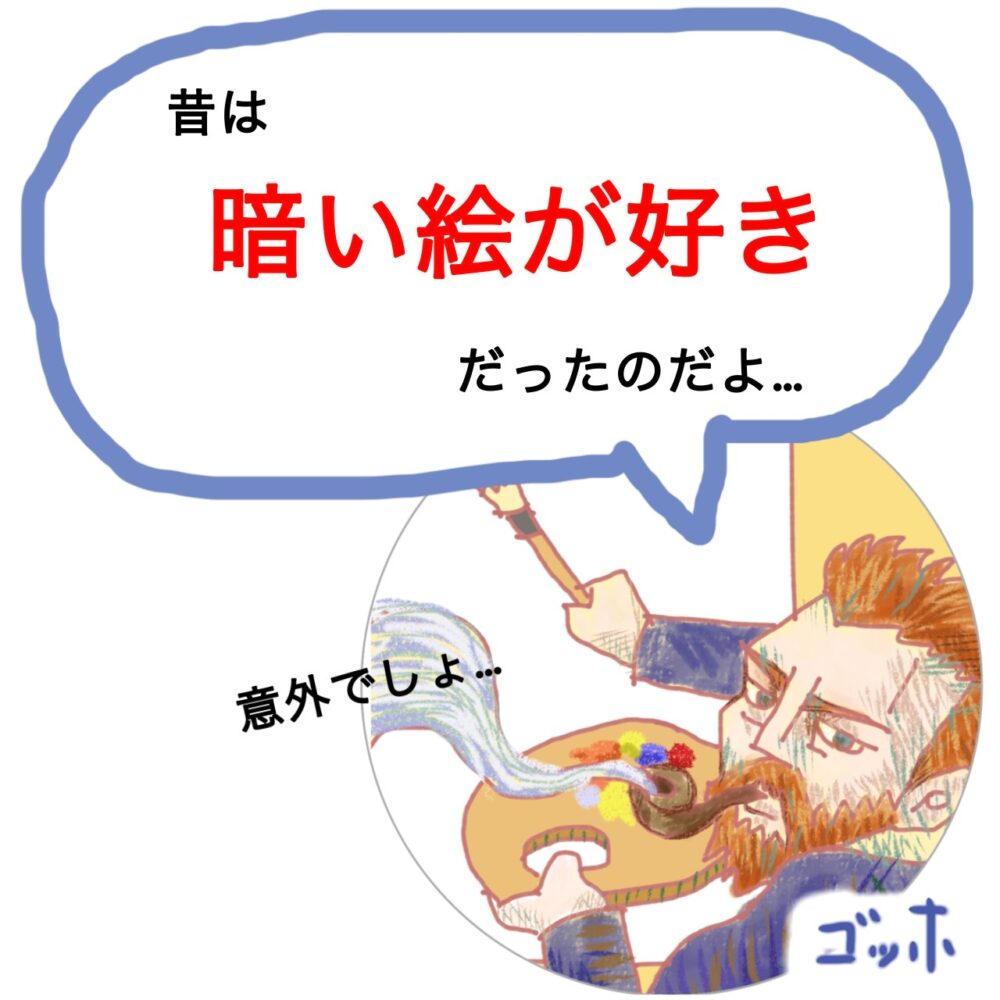
パリ時代:印象派との出会いで一変!

その後ゴッホが向かったのは、芸術の中心地・パリ。そこには弟のテオが住んでおり、経済的な理由だけでなく、心のよりどころとしても彼を頼っての移住でした。
当時のパリでは、モネやルノワールに代表される「印象派」が大流行中!
明るい光、軽やかな色づかい、そして筆のタッチまで自由なそのスタイルに、ゴッホは大きな影響を受けます。ここから彼の画風はぐっとカラフルに、表現も豊かになっていきます。
さらに、ゴッホが夢中になったのが“日本の浮世絵”。
広重や英泉の版画に魅了され、何枚も模写したことが知られています。輪郭をくっきり描き、平面的に色を塗る浮世絵のスタイルは、のちの彼の作品にも色濃く反映されていきます。
このパリ時代を経て、いよいよゴッホは南仏アルルへと向かい、あの鮮やかな「夜の絵」を描くようになるのです。

アルルにて
アルルと日本
1888年2月、ゴッホはついにパリを離れ、次なる舞台――南フランスのアルルへと向かいます。
パリで浮世絵に出会い、日本への憧れを強めていたゴッホ。
彼にとって、南仏の明るく澄んだ風景は、どこか“日本らしさ”を感じさせるものでした。
実際、弟テオに宛てた手紙の中で、こんなふうに語っています。
「雪の中で雪のように光った空をバックに白い山頂をみせた風景は、まるでもう日本人の画家たちが描いた冬の景色の様だった。」
フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第四巻」みすず書房 1984年10月22日発行改版第一刷、1338頁

彼は、日本の浮世絵に見られる特徴――
特に、はっきりとした輪郭線や色面を使って空間を表現する手法に強く影響を受けていました。
色面と色面を隣り合わせに置くことで、より鮮やかなコントラストが生まれる。
この“色の対比”がもたらすインパクトに、ゴッホは魅せられていったのです。
そして、その成果が最初に花開いたのが、アルルで描いた“夜景”の作品でした。
アルルの夜景
アルルの生活の中で、ゴッホがとりわけ心を奪われたのが、夜の風景でした。
パリと違い、街灯の少ないアルルの夜は本当に暗く、だからこそ星たちはくっきりと、宝石のように輝いて見えました。
そんな幻想的な夜空に、ゴッホは新たな色彩表現の可能性を見出していきます。
「ぼくにはよく夜の方が昼よりもずっと色彩が豊かであり、もっとも強い菫(すみれ)や青や緑の色合いがあるように思えることがある。」
フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第六巻」みすず書房 1984年12月20日発行改版第一刷、1930頁
この言葉が示すように、ゴッホにとって夜は、決して「暗い」時間ではありませんでした。
むしろ、昼には見えない“夜だけの色”がある――そんな思いで彼はキャンバスに向かっていたのです。
こうして生まれたのが、《夜のカフェ・テラス》や《ローヌ川の星月夜》といった名作たち。
彼の中で「夜」が新たな色の宇宙となり、作品にいっそうの深みを与えていった瞬間でした。

《夜のカフェ・テラス》を描く

現場主義、時間にもこだわる
そして生まれたのが、あの《夜のカフェ・テラス》です。
この作品は、ゴッホが当時住んでいた「黄色い家」から南西に1kmほどの場所、プラス・デュ・フォルム広場にあるカフェをモデルに描かれました。
彼は印象派の画家たちのように、絵具道具を持って現地へ出かけ、その場で制作を行いました。しかもこだわったのは「時間」。日が沈んだあとの、まさに“夜の本番”に描きはじめたのです。
「夜景を実地で描くのは大変おもしろい。従来人がデッサンしたり描いたりしたものは、簡単にスケッチをした後で、真昼間やったものだ。しかし僕は現場で事物を描くことに喜びを覚えている。」
フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第六巻」みすず書房 1984年12月20日発行改版第一刷、1931頁
実際に夜の現場で描くことには苦労もありましたが、だからこそ、星空やテラスの灯りが生み出す繊細な色のゆらめきを、彼は間近で捉えることができたのです。
「この夜の絵には黒が全くなく、専ら美しい青と菫色と緑で描かれ、周囲の光に照らされた広場は薄い硫黄色と緑がかったレモン・イエローを帯びている〔……〕もちろん色の質を正しく見分けがたいから、暗がりの中では、青を緑と間違えたり、青薄紫をピンクの薄紫と間違えたりすることがあるのは事実だ。しかしそれは一本の蝋燭でも極めて豊かな黄色やオレンジ色を与えるのに、あわれな青ざめた白っぽい光りで夜景を描く従来の因習を脱する唯一の方法だ。」
フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第六巻」みすず書房 1984年12月20日発行改版第一刷、1931頁
色のハーモニーが魅せる世界

画像:by +- at Japanese Wikipedia
この作品でまず目を引くのが、青と黄色の強烈な対比。そして、それが決してバラバラではなく、見事に調和している点です。
黄色と青は、色相環(色を円形に並べた図)で正反対の位置にある「補色」の関係にあります。ゴッホはこの補色の力をうまく使い、画面に独特の緊張感と調和を生み出しました。
とはいえ、ただ色をぶつけているだけではありません。テラステントのオレンジ、壁の光と影が混じって生まれる黄緑、遠くの建物の沈んだ青、地面に反射した菫色など、細やかな色の変化が画面全体を包んでいます。
まさに、色の響き合い——それがこの作品の最大の魅力です。
夜の制作スタイルもゴッホ流?
ちなみに、ゴッホは街灯の下でこの作品を描いたそうですが、なんと「麦わら帽子に蝋燭をくくりつけて描いていた」なんていうエピソードもあります。
真偽のほどは定かではありませんが、「ゴッホなら本当にやってそう」と思わせてしまうところが、また彼らしいですよね。

その他の「夜」の絵
《ローヌ川の星月夜》

《夜のカフェ・テラス》の他にも、ゴッホは夜をテーマにした作品をいくつか残しています。そのひとつが《ローヌ川の星月夜》です。
この作品は《夜のカフェ・テラス》と同じ時期に描かれたもので、舞台となっているのは、ゴッホが住んでいた「黄色い家」のすぐ西側を流れるローヌ川。夜空に輝く星々と、穏やかな水面に映る街の灯りが幻想的に描かれています。
ここでもゴッホの色彩センスが光ります。ただし、《カフェ・テラス》のように黄色を大胆に塗り分けるのではなく、点や線を重ねる繊細なタッチで、光を表現しているのが特徴です。
特に注目したいのが、水面に映り込んだ街灯の光。筆を小刻みに動かして描かれたその輝きは、前景に近づくほど青と混ざり合い、深い夜の静けさと温もりが同居するような、不思議な色のグラデーションを生み出しています。
ちなみにこの作品、《ローヌ川の星月夜》は翌年1889年、パリで開かれたアンデパンダン展(無審査・自由出品の美術展)にも出品され、来場者から好評を得ました。
《夜のカフェ》

タイトルだけを見ると、つい《夜のカフェ・テラス》と混同しがちですが、《夜のカフェ》は屋外ではなく、“室内”を描いた作品です。
舞台となっているのは、あの「黄色い家」の近くにあった「カフェ・ド・ラ・ガール」。ここは夜通し営業していて、宿がない人たちが眠る場としても使われていた、ちょっとワケありな雰囲気のカフェです。ゴッホはそんな怪しげな場の空気をしっかりと捉えるため、3日間徹夜してこの作品に取り組みました。
「僕は『夜のカフェ』で、カフェとは人々が身を持ち崩し、気狂いになり、罪を犯すところだということを表現しようと努めた。」
フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第五巻」みすず書房 1984年11月20日発行改版第一刷、1476頁
この絵の大きな見どころは、やはりゴッホらしい“色で語る”表現力。カフェの退廃的なムードを出すために、壁の赤と天井の緑という強烈な補色をぶつけ合い、空間にどこか不安で落ち着かない雰囲気を生み出しています。
「ぼくは人間の恐ろしい情熱を赤と緑で表現しようと努めた。広間は血紅色と鈍い黄、中央に緑の玉突台があり、オレンジと緑の光線を放つレモン黄のランプが四つある。眠りこけている与太者とか菫と青のがらんとした侘しい広間とか、あらゆるところで緑と赤との衝突があり対立があるのだ。
フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第五巻」みすず書房 1984年11月20日発行改版第一刷、1473頁
もうひとつ注目したいのは、ランプの光の描き方です。ゴッホはカフェの空気をより不気味に見せるために、ランプの光を揺れ動くような筆致で表現しています。
当時の美術界では、「印象派」が最先端のスタイルでした。外光の変化を捉えるその手法は従来の古典絵画とは大きく異なっていましたが、それでもなお、「見たままを描く」という意味では、写実の枠にとどまっていたともいえます。
その点、《夜のカフェ》におけるゴッホの光の表現は、明らかに“見たまま”を超えたもの。
彼の筆致は、心の内にある感情や場の空気そのものを可視化するようなものであり、のちの「表現主義」へとつながる、ひとつの先駆けだったといえるかもしれません。
まとめ
今回は、ゴッホの“夜”の作品たちをご紹介してみましたが、いかがでしたか?
パリで印象派の影響を受けたゴッホは、明るく鮮やかな色づかいを取り入れるようになったのですね!
そして、何より大きな転機となったのが、日本の“浮世絵”との出会い。写実的だった画風は、色彩を意識した平面的で装飾的な表現へと変化し、《夜のカフェ・テラス》や《ローヌ川の星月夜》といった名作が生まれていったのです。
さらに、ゴッホらしい独自の表現スタイルが生まれたのも、こうした“夜”の作品たちからでした。
モチーフの性格や空気感を伝えるために、色彩や筆づかいに感情を込める——この手法は、後のゴッホ作品を語るうえで欠かせない大きな特徴となっていきます。
このあとゴッホがどんな道を歩んでいくのか、気になる方はぜひ他の記事もご覧ください。
それではまた、次回の記事でお会いしましょう!
「アルル時代」の後、「サン・レミ、オーヴェル時代」を解説する記事です。こちらからどうぞ!



コメント